【CEATEC 2025レポート】地方創生DXの最前線-デジタルが変える地域・行政・暮らしの未来

最先端の技術や製品が一堂に会する、日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」(会期:2025年10月14日(火)~17日(金)、会場:幕張メッセ)が開催され、さまざまな産業・業種の関係者が来場した。
本記事では、10月14日に行われたセッション「DXが導く地方創生2.0~先進事例に学ぶ」の模様をレポートする。
日本が直面する最重要課題のひとつが、「住み続けられる活力ある地域社会」の構築である。
政府は「地方創生2.0」を掲げ、災害に強く、働く喜びと暮らしの安心を両立できる地域づくりを推進している。
一方で、地域産業の付加価値向上、交通・物流など生活基盤の維持、若い世代や女性に選ばれるまちづくりなど、地域が抱える課題は多岐にわたる。
こうした中で注目を集めているのが、AI・ロボティクス・ドローンなどの先進デジタル技術だ。
これらは地域課題の解決に不可欠なツールであり、新たな産業や働き方を創出する“変革のエンジン”でもある。
セッション「DXが導く地方創生2.0~先進事例に学ぶ」では、自治体・企業・市民の各立場から、デジタル技術をいかに活用し、どのように多様な主体が協働して地域を再生していくのかが議論された。
登壇者は以下のとおり。
三浦 明 氏(デジタル庁 統括官 国民向けサービスグループ長)
浅野 大介 氏(石川県副知事 兼 CDO)
北野 宏明 氏(沖縄科学技術大学院大学 教授 / 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)代表取締役社長)
関 治之 氏(一般社団法人コード・フォー・ジャパン 代表理事 / Japan CDO Community コアメンバー)
田中 淳一 氏(株式会社うるら 代表取締役会長 / 前 三重県 最高デジタル責任者(CDO) / Japan CDO Community コアメンバー)
モデレーター:吉田 真貴子 氏(Japan CDO Community 代表世話人 / 全国地域情報化推進協会 顧問)
能登の創造的復興に向けて-浅野大介氏が語るDXと地域再生の挑戦
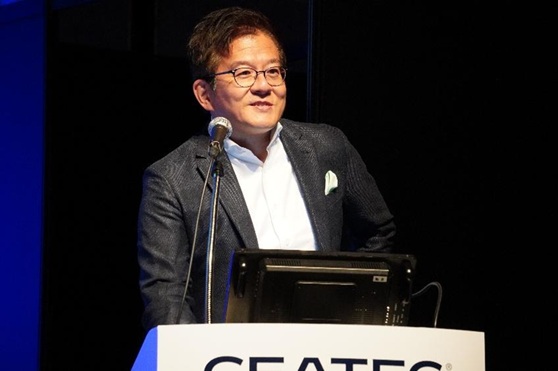
能登半島地震と豪雨を経て、石川県は「復旧」から「創造的復興」へ。
浅野大介 副知事兼CDOが、先回り・組み合わせ自在・一発解決を核に、官民越境の連携とデジタル(通信・ドローン等)を“命と暮らし”の基盤として再設計する戦略を語った。
被災の現場から生まれた“創造的復興”のビジョン
セッション冒頭、浅野氏は石川県副知事に就任してわずか2カ月後に直面した「令和6年奥能登豪雨」について振り返った。
「副知事就任直後の9月に奥能登地域で発生した豪雨で、災害からの復旧作業が振り出しに戻ってしまいました。地震で被災した一部の地域に、土砂が民家や集落を襲い、またゼロからのスタートとなったのです」
同年1月1日に発生した能登半島地震。住宅の倒壊、地盤隆起、液状化など甚大な被害から少しずつ復旧が進み始めた矢先に、再び自然災害が発生した。
「石川県は“復旧”ではなく、“創造的復興”へと転換しなければならない」と浅野氏は決意を新たにしたという。
「創造的復興」とは、単なる原状回復ではなく、地域の強みや魅力を再発見し、デジタル技術や新たな連携の仕組みを活用して、より豊かで持続可能な地域社会を再構築する取り組みだ。1995年の阪神・淡路大震災後に兵庫県が提唱したのが始まりとされている。
石川県が策定した「石川県創造的復興プラン」の全容については、ぜひ石川県のHPを確認していただければと思うが、本セッションで浅野氏が紹介したのは、石川県のDX推進ビジョンである。
デジタル化とDXの違い──「先回り」「組合せ自在」「一発解決」の行政へ
浅野氏はまず、「デジタル化」と「DX」の違いを明確にした。
デジタル化:紙の申請書をオンライン化する、窓口業務を電子化するなど、既存業務の効率化・省力化を図る取り組み。
DX:行政の仕組みそのものを再構築し、社会の在り方を変革すること。
この区別を踏まえ、石川県が目指すDXの方向性を象徴するのが、「先回り」「組合せ自在」「一発解決」という三つのキーワードである。
先回り
AIやデータ分析を活用し、行政を“事後対応”から“予測対応”へと転換する。災害や福祉、インフラ老朽化などのリスクを事前に検知し、被害を最小限に抑える。
「人間の経験や勘に頼るのではなく、デジタルの記憶力・処理力・予測力を活用して先手を打つ行政をつくる」と浅野氏は語った。
組合せ自在
行政、民間、地域住民がそれぞれのデータやリソースを標準化された仕組みの上で共有・連携を可能とし、分野や組織の壁を越えて新たな解決策を生み出す“協働のプラットフォーム”を構築する。
たとえば、観光データと交通情報、一次産業の生産データを連携させることで、地域産業に新たな付加価値を創出できる。
一発解決
縦割りで複雑化した行政システムを改め、課題ごとに最適な解決策を「ワンストップ」で提供する考え方だ。
従来のように「この問題はこの部署」「別の課題は別の申請」といった分断をなくし、課題を一気に解決できる行政サービスを目指す。
これら三原則の狙いは、単にデジタルを導入することではなく、「デジタルを前提とした行政の再設計」にある。
浅野氏は「効率化ではなく、先手を打つ行政へ。これが本当のDXだ」と力を込めた。
越境が生む力-現場とデジタルがつなぐ創造的復興の最前線
災害復興の現場では、行政の枠を超えた「越境力」が試される。
災害時、浅野氏は国・県・市町、そして民間やNPOなど立場の異なる組織をつなぐ役割を担ってきた。
「官民で共通の言葉を見つけ、遠慮や依存を捨て、最上位の目標に全員がコミットすることが大切です。県も市町も民間も、共通の言葉を持って同じゴールに向かうことで、一発解決できる組織運営を目指していました」と語る。
被災地では、こうした越境的な連携がソーシャルキャピタル(社会関係資本)として機能し、行政の限界を超える力を発揮した。
実際、奥能登の現場では、NPOや企業、地域団体が連携し、毎朝7時半からオンラインで情報共有を行う仕組みを立ち上げた。
行政が精緻に整理した報告だけでは見えない「生の現場情報」を加えることで、政策判断の精度が格段に高まったという。
浅野氏は「磨かれた情報と生の情報が組み合わさって初めて“真の情報”になる」と強調する。
現場の声を政策に反映させた象徴的な事例が、いわゆる「縦割り補助金」の見直しである。
被災地域では、宅地・道路・農地など分野ごとに異なる補助金制度が適用され、事務負担が膨大になっていた。
これに対し浅野氏は、「同じ川から流れた土砂なのに、使える制度が違うのはおかしい」と訴え、国との交渉を重ねた。
その結果、三つの省庁が交付要綱を統一し、同一内容の補助金として運用できるようになった。
現場の理不尽を吸い上げ、国の制度を動かす──まさに“現場発の政策変革”である。
一方で、デジタル技術の導入も復興の大きな支えとなっている。奥能登豪雨では通信網が寸断されたが、能登半島地震での教訓を踏まえ、県は衛星通信Starlinkを3キャリア合同で緊急配備し、通信復旧をわずか3日間で実現した。
さらに、ドローンを活用して農産物の運搬や被害状況の把握を行い、今後は官民が共同で運用する「ドローン・プラットフォーム」の構築を進めている。
警察・消防・インフラ事業者などを含む広域連携により、平時と災害時の両方で活用できる仕組みを目指している。
浅野氏はこれらの取り組みを「デジタルライフライン」と呼ぶ。通信やデータ、ドローンを“命と暮らしを守る基盤”として位置づけ、教育・医療・介護・防災などあらゆる領域でデジタルを活用し、県・市町・民間が一体となって地域の安心を支える。
その先に見据えるのは、単なる復旧ではなく「創造的復興」──災害を契機に地域のあり方そのものを再設計し、より強く、よりしなやかな地域社会を築くことである。
浅野氏は最後にこう語った。
「デジタルの力で地域を再生し、石川から新しい復興モデルを発信したい。能登の挑戦を、未来の地方創生の原型にしたい」。
その言葉には、被災地の痛みを知る行政人としての覚悟と、未来への確かな希望が込められていた。
伝統とテクノロジーが交わる日本の未来-北野宏明氏が語る「トラディション×テロワール×テクノロジー」の可能性

本セッションにドバイから参加した北野宏明氏は、「AGI(汎用人工知能)」時代の到来を見据えつつ、日本が持つ伝統や食文化、歴史といった価値をテクノロジーの力で新たに押し上げる必要性を語った。
世界のAI覇権争いに“正面から挑まない”という選択
北野氏が最初に指摘したのは、AIをめぐる国際競争の現実である。
「GoogleやOpenAI、イーロン・マスク氏らが主導するAGI分野では、莫大な投資とプラットフォーム力を背景に、もはや真正面から勝負できる領域ではない」と断言する。
では日本はどう向き合うべきか。北野氏は「AIではないもので勝負する」と強調する。
クラウド上で誰もが利用できるAIサービスとは異なり、「その土地にしかないもの」こそが日本の最大の強みだという。
神社や神話、伝統工芸、食文化など、長い歴史の中で育まれてきた“人と土地の結びつき”──すなわちヒストリーとトラディションが、日本の独自性と価値を支える基盤になると語った。
北野氏が提唱するのは、「トラディション(伝統)」「テロワール(土着性)」「テクノロジー(技術)」の融合である。
神話や文化といった伝統、地域に根ざした素材や人々の営み、そして現代的な技術・ブランディング・資本戦略を組み合わせることで、失われつつある産業に新しい価値を吹き込む。
北野氏は、伝統工芸の技術・製品が建築素材や高級ホテルの内装に採用された事例を挙げ、地域ブランドを国際市場向けに再構築するなど、テクノロジーを「リフレーミング(物事を別の視点や枠組みから捉え直す)」ための道具として活用する重要性を訴えた。
「ここでのテクノロジーとは単なるITのことではない。経営やマーケティング、資金調達も含めた“新しい知の技術”であり、これを導入することで伝統産業の価値を何倍にも高められる」と北野氏は語った。
日本の地域が持つ“未開のポテンシャル”
北野氏は、自身が訪れた瀬戸内・京都・伊勢志摩の例を挙げ、「この地域一帯には、歴史・食・自然のいずれを取っても世界有数の資源が眠っている」と述べた。
ブランディング次第で、その価値はさらに高まるという。
そして、「AIやDXは“核となる文化や価値”があってこそ意味を持つ。伝統や地域性があって初めて、テクノロジーは生きる」と強調。
テクノロジーを主役にするのではなく、人と土地の物語を中心に据えることで、持続可能な日本の再創造が可能になると結んだ。
実験する自治から始まる共創―関治之氏が語る「関係性の再設計」と新しい地域のかたち

「DXは課題を解く道具ではなく、構造を変えるための契機だ」
コード・フォー・ジャパン 代表理事・関治之氏は、地域のDXが抱える限界を指摘し、自治のあり方そのものを問い直す必要があると語る。
課題解決のためのDXではリソースが足りない
関氏は、多くの自治体DXが「課題解決のための手段」として始まり、やがて“目的化”してしまっている現状に警鐘を鳴らす。
「課題を一つずつ見つけてDXで解決していくやり方では、リソースが持たない。今必要なのは、課題そのものを生み出す構造を変えることだ」と強調する。
そのために必要なのが、“自治”の再定義である。
外部の専門人材や関係人口を呼び込むだけでは、地域の構造は変わらない。むしろ、地域の内部にいる人々が自ら関係性をつくり直し、新しい自治のかたちを構築していくことが重要だと関氏は指摘する。
「誰が何をやるかを指示するのではなく、共に考え、共に動く。そこからソーシャルキャピタル(社会的資本)が生まれる」と語った。
「Kuu Village」に見る新しい関係づくりの実験
新しい自治のかたちを探る実践例として紹介されたのが、奈良県月ヶ瀬で行われた「Kuu Village」プロジェクトだ。
関氏を含む約40人が1週間にわたり共同生活を送り、地元住民と共にサウナ小屋を建て、井戸を掘り、地域の歴史を学んだ。デジタルではなく、“手を動かす”ことで生まれるリアルな関係性を重視した取り組みである。
Web3関連のエンジニア、研究者、言語学者など多様な人々が集い、「この地域にとって新しいコモンズ(共有資源)とは何か」を議論した。
その過程で、感謝の気持ちを暗号技術で表現するなど、テクノロジーも“人をつなぐ媒介”として活用された。
「サウナを作ろうと言えば、誰でも参加できる。デジタルの入り口では届かない層も、自然に関われる」と関氏は語る。
関氏が目指すのは、“実験できる自治”だ。
職員や住民、外部人材といった立場を超え、一人の人間として地域を考える。評価や成果よりも「感謝が循環する関係性」を育てることで、地域は持続的に活力を生み出せるという。
「自治とは、共に暮らし、手を動かし、学び合うこと。そこにこそ、真に豊かな関係人口が育つ土壌がある」
関氏の言葉は、デジタルよりも“人間の温度”を取り戻す地域づくりへの指針として響いた。
住民と行政がつくる協働のDX-田中淳一氏が語る「三重県明和町モデル」と信頼のデジタル社会

「中に入らないと構造は変わらない。」
三重県の前CDO・田中淳一氏は、関治之氏の言葉に深くうなずきながら、自らも現場に入り込み、共に考え、共につくる、“あったかいDX”を実践している。
住民起点で変わる行政サービス
セッションで田中氏は、現在携わっている人口約2万人の三重県明和町での取り組みを紹介した。
明和町では、行政手続きを「役場でやるもの」から「住民が自分でできるもの」へと転換するため、住民起点のDXを進めている。
その第一歩として、子育て世代向けのデジタル申請を中心に、誰でも簡単に使える行政サービスを整備した。
しかし、課題は“使ってもらうこと”にあった。
「住民の多くが、行政手続き=窓口というイメージを強く持っている」と田中氏は語る。
そこで、同じ子育て世代の住民を「子育てDXアンバサダー」に任命。
住民同士が教え合いながら、スマートフォンでできる行政サービスを広めていく仕組みをつくった。
その結果、町民の「子育てDX」の認知度は70%を突破。
アンバサダーがユーザーテストにも参加し、手続き画面の言葉遣いや導線を共に改善したことで、住民に寄り添ったDXが実現した。
「住民との協働こそが、信頼と利他に基づくソーシャルキャピタル(社会的資本)そのもの」と田中氏は語る。
デンマークに学ぶ“信頼のDX”
明和町の取り組みの発想源は、デンマークの「デジタルアンバサダー」制度にある。
デンマークでは、行政と市民が協働しながらデジタル化を進めており、日本のように“窓口を残す”のではなく、住民自身が学び合い、支え合いながらデジタル社会を築いている。
田中氏はこう語る。
「みんなで考え、みんなでつくる。その精神こそ、地域DXの原点です」
テクノロジーを“押し付ける”のではなく、人と人との信頼関係を起点に社会を進化させていくこと。
それが、田中氏の掲げる“あったかいDX”の核心である。
「デジタル公共財」で広がる共創の輪-デジタル庁 三浦明氏が語る地域と行政の協働モデル

「書かない窓口」など、行政のデジタル化は全国で進んでいる。
だが、デジタル庁が目指すものは、DXによる単なる効率化ではない。
地域がデジタルを“共通の財産”として活かし、行政・企業・市民が共に育てていく社会だ。
デジタル庁 国民向けサービスグループ長・三浦明氏が、その構想と実践を語った。
「デジタル公共財」を共に使う社会へ
三浦氏は、戦後80年にわたる制度設計を振り返りながら、「日本の行政サービスは特定の課題に最適化されている一方で、複合的な問題に弱い」と指摘する。
社会保障分野を例に、医療・介護・福祉・働き方など、複数の要因が絡み合う課題が噴出する現代社会では、従来の“縦割り”構造では対応しきれない、いま求められるのは、分野も越えた“横割り”で課題を解決できる新しい仕組みの設計だという。
その中で、デジタルが果たす役割は「暮らしを支える」と「稼げる社会をつくる」の両面にある。
デジタル庁は、地域の幸福度(ウェルビーイング)を測定するツールを提供し、住民自身が“どんな地域にしたいか”を議論できる環境づくりを支援している。
「地域が自分たちの未来像を共有し、その上で一人ひとりに最適化されたサービスを届ける社会をつくりたい」と三浦氏は語る。
そのために欠かせない考え方が「デジタル公共財」である。
「デジタル公共財」とは、マイナンバーカードのようなデジタルインフラを基盤に、全国の自治体が共通して利用できるサービスを整備する構想だ。
「新しいシステムを競い合ってつくるのではなく、共同利用できるものは、みんなで“割り勘”して使う時代に入った」と三浦氏は強調する。
富山県朝日町に見る「共通基盤」の力
象徴的な事例として紹介されたのが、富山県朝日町の取り組みである。
マイナンバーカードを活用し、子どもの見守りから高齢者の健康管理、地域通貨による買い物や移動支援までを統合。
行政・民間・住民が協働し、「暮らし全体を支える仕組み」を実現している。
「行政の縦割りではできないことを、横断的な組織と民間の力で実現している。これこそが“デジタル公共財”を活かした地域共創の形です」と三浦氏は語る。
デジタルは“使う”から“共に育てる”へ──。
デジタル庁が描く地方創生の未来は、共助と信頼を基盤にした“共有のデジタル社会”の実現に向かっている。
テクノロジーの先にある“人と地域が主役”の地方創生
本セッションでは、行政・企業・市民が垣根を越え、デジタルを共通基盤として活かす地方創生の新たな姿が語られた。能登の「創造的復興」に見る現場主導のDX、北野氏による地域資源の再定義、関氏・田中氏の“関係性のDX”、そして三浦氏の「デジタル公共財」。それぞれの実践が示したのは、テクノロジーではなく“人と地域が主役”のDXである。

モデレーターを務めた吉田真貴子氏は、これらの議論を受けて「究極的にはコアバリューをどう共有できるかが重要」と述べ、コアバリューの実現のためにあらゆる境界を超える必要があると指摘した。具体的には、平時と有事の両方でシステムを活用する「フェイズフリー」、官と民の役割を超える「セクターフリー」、異なる地域間の協力を実現する「リジョンフリー」という3類型の考え方を提示した。立場や領域を超えて自由に語り合い、共に価値を育むことが、真の地方創生につながるという視点である。
人と地域、そしてデジタルが交わることで生まれる共創の力。そこから新しい日本の地方創生のかたちが動き出している。